箱庭から遠く離れた地にて、一人の母が涙を流した。瞳から流れる涙は透明ではなく濁った褐色で、乾ききった頬を伝った。顎まで伝うことなく、流れた涙の全ては乾いた頬に浸透して消えた。
彼女は、かつて感情の巨木と呼ばれた大樹に捕らわれ、同化しようとしていた。彼女の他にも数え切れないほどの人々が捕らわれている。人々は巨木に吊るされ、土気色の肌には巨木の根が張っている。それは教会の下にいた神々だった者と同じ様だった。死んではいないが、決して生きているとも言えない。
そんな彼女が涙を流したのは奇跡だった。しかし涙を流すきっかけを考えれば、奇跡などという美しい言葉とは似ても似つかない。涙を流す要因となったのは瘴気水子の子どもたちだった。
時代は感情の巨木が変異し始めた時代まで遡る。当時の人々は感情の巨木の変化は巨木の怒りを買ったことと捉え、生贄を捧げて巨木の許しを得ようとした。様々な人が生贄に捧げられたのだが、彼女も捧げられた生贄の一人だった。
当時、瘴気に適応するために様々な動植物が変異を起こしており、生贄に捧げられた人々は感情の巨木が吐き出す瘴気の影響を直接受けてしまった。その結果四肢が複数本生えた姿や、逆に四肢が異常なまでに退化した姿、人ではない獣の姿に成り果てた。
余談だが、クロウはこの瘴気による変化を利用して、ヴァンの両親を魔猿へと変異させたのだ。
さて、瘴気の影響を直接受けた彼女にはどのような変化が起こったのだろうか。生贄として捧げられた時、彼女は気づいていなかったが、彼女の身体には新たな生命が宿っていた。幸い母体である彼女には大きな変化はなかったが、瘴気の影響を強く受けたのは彼女の体内にいる子供だった。
瘴気の影響を受けた胎児は異常な分裂を繰り返し、最終的に十二人の兄妹となった。子どもたちは胎盤を通じて栄養を求めるが、巨木に侵された彼女の身体から大量の瘴気が流れ込んだ。そして子どもたちは奇妙な変異を起こし、彼女の腹部はどんどん大きくなっていった。
巨木の生贄に捧げられてからも彼女の意識ははっきりしていた。そのため彼女はおぞましいほどに膨らむ腹部を見て、その中で蠢く命の存在を知った。
他者から見れば不気味に映る十二人の子どもたちでも、彼女はどんな姿であろうと自分の子供だとして、子どもたちを愛した。その奇怪な愛情は魔力という形を持って現れた。もしかすると、それほどの愛情を抱かなければ、全身を巨木に侵されながら意識を保つことができなかったのかもしれない。
順調と言うには歪みすぎているが、それでも子どもたちは成長していった。しかしある時、身体の中で成長する十二人の子どもたちの大きさに彼女の身体が限界を迎えた。子どもたちは彼女の腹部を割って体外に出てきたのだ。
彼らはやはり奇妙な体躯をしていた。他の兄弟の腕を合わせて七本の腕と十五本の足を生やした子や他の子ども達に圧迫されアメーバ状に変形した子、内臓や感覚器が体表からはみ出した子などだ。
その子どもたちの中にはヴェリドが持っていた髑髏の首飾りも含まれている。十二人の兄弟たちの末っ子は、既に発達した兄弟たちの隙間を埋めるように小さな頭と脳天から直接生える胎盤のみを自分の身体としたのだ。
不完全な十二人の子どもたちは生まれながらに死んでいる。愛情から来る、魔力という名のへその緒によって十二人の子供たちは死にながら生きることができた。その様子からいつしか十二人の子どもたちは瘴気水子の子どもたちと呼ばれるようになった。
瘴気水子の子どもたちは母親の魔力によって守られている。しかし、複雑な変異を起こした子どもたちは体外に出てしばらくすると自己崩壊を始めた。彼らは母親の魔力があるとはいえ、外の世界に適応することはできなかったのだ。
複雑な変異を起こした子どもたちは初期に分裂した子どもたちが多い。複雑に発達した身体は外の世界では維持できなかったのだ。一方で後期に分裂した子どもたちは比較的多くの子どもたちが生き残っていた。狭い空間で発達するために身体の大部分を退化させて成長していったからだ。
したがって自己崩壊を起こさず残った子どもたちの多くは身体の機能を大きく欠損していた。残った子どもたちは自分で移動することができず、その奇妙な姿から処分されてしまう子どもがほとんどだった。そして趣味の悪いアクセサリーとしてみなされた末っ子だけが人の手を渡ってきたのだった。
長年人の手を渡ってきた瘴気水子の末っ子だったが、サーノティアとの戦闘の末に死んでしまった。最後の子どもが死んでしまい、母親の魔力はもはや機能しなくなった。
巨木に捕らわれた瘴気水子の母はその瘴気によって変異した。そして巨木から逃れてきた人類が築いた箱庭にも瘴気の変化が及び始めていた。


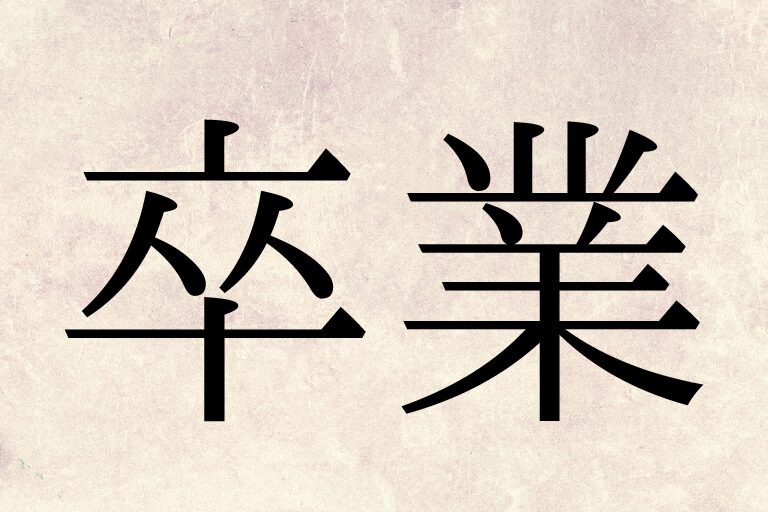
コメント